『東京社会辞彙』
自由価格図書◇本体6500円【割引き前税込価格:13650円】、湘南堂書店、B5変形 / 1088p、1987 http://www.bk1.co.jp/product/00550761
内容説明:明治時代の東京における社会を知る事典、当時の東京の様子が手にとるように分かる。目次に、皇族を始めとする人物の部を始め、銀行会社商店の部、官衛学校の部、名所 古蹟、神社、仏閣、地名之部、劇場病院市場割烹店其他之部があり、それぞれの中でイロハ順に引けるようになっている。写真も多数収録。大正2年刊の復刻。
『心とことばの起源を探る』
『心とことばの起源を探る 文化と認知』〔シリーズ 認知と文化〕マイケル・トマセロ/著 西村義樹・大堀壽夫・中澤恒子・本多啓/訳、勁草書房、2005年10月下旬、3150円(税込)◇ヒトはなぜ言語を使えるようになったのか? 人間に特有の認知能力を解き明かし、大胆かつ緻密な仮説によって進化の最大の謎に迫る!
原書:Michael Tomasello, The Cultural Origin of Human Cognition, Harvard University Press, 1999

- 作者: マイケル・トマセロ,大堀壽夫,中澤恒子,西村義樹,本多啓
- 出版社/メーカー: 勁草書房
- 発売日: 2006/02/14
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 31回
- この商品を含むブログ (29件) を見る

The Cultural Origins of Human Cognition
- 作者: Michael Tomasello
- 出版社/メーカー: Harvard University Press
- 発売日: 2001/03/02
- メディア: ペーパーバック
- クリック: 2回
- この商品を含むブログ (5件) を見る
『人はなぜ恋に落ちるのか?―恋と愛情と性欲の脳科学』
ヘレン・フィッシャー著、大野晶子 訳、ソニー・マガジンズ、2005/09、357p 本体2000円[原書名:WHY WE LOVE〈Fisher, Helen〉]
◇「つい最近、激しい恋に落ちた人はいませんか?」ニューヨーク州立大学の掲示板にこんなチラシが貼られた。恋に落ちる、とは生物学的にどのような現象なのだろう?恋をしている人の脳をスキャニングするとなにが見えてくるだろう?解明されていく恋の脳内メカニズム―それは、驚きの連続だった。脳内メカニズムで恋の疑問を解く。
第1章 恋に落ちたらどうなるか―特別な心理状態 第2章 動物たちの恋愛―高揚、忍耐、独占欲 第3章 恋する脳をスキャンする―愛の化学作用 第4章 愛が織りなす網の目模様―性欲、恋愛感情、そして愛着 第5章 なぜ「あの人」を好きになるのか―恋人選びのルール 第6章 人はなぜ恋をするのか―恋愛の進化 第7章 失恋とはなにか―拒絶、絶望、怒り 第8章 ロマンスを長つづきさせる―恋わずらいに効く薬 第9章 それでも人は恋に落ちる―愛の勝利

- 作者: ヘレンフィッシャー,Helen Fisher,大野晶子
- 出版社/メーカー: ソニーマガジンズ
- 発売日: 2005/09
- メディア: 単行本
- 購入: 7人 クリック: 121回
- この商品を含むブログ (17件) を見る

Why We Love: The Nature and Chemistry of Romantic Love
- 作者: Helen E. Fisher
- 出版社/メーカー: Henry Holt & Co
- 発売日: 2004/02/01
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログ (1件) を見る
【関連書籍】

- 作者: ヘレン・E・フィッシャー,吉田利子
- 出版社/メーカー: 草思社
- 発売日: 1993/05
- メディア: 単行本
- 購入: 10人 クリック: 32回
- この商品を含むブログ (17件) を見る
『17歳の軌跡』
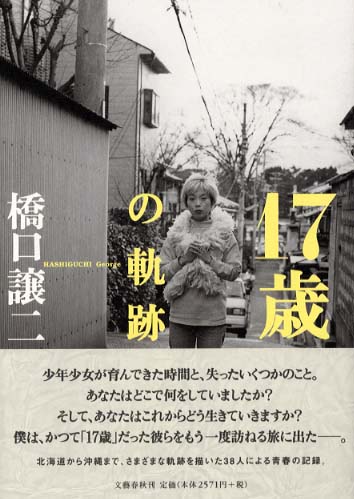
橋口譲二 著、文芸春秋、2000/09 511頁、A5判 税込2700円 ISBN:4163565507
from http://www.bunshun.co.jp/book_db/html/3/56/55/4163565507.shtml
八八年、全国の17歳の肖像で構成された写真集『十七歳の地図』(現在は『17歳』として復刊)を発表した橋口さんは、十年目の正月、登場人物全員に手紙を書きました。「今、どうしていますか?」と。
そして「17歳」をひとつの記号と見なす昨今の風潮に異を唱える写真家は、かつての「17歳」たちを再訪する旅に出ました。礼文島へ、沖縄・名護へ、そしてハリウッドへ−−。個性的な彼らの肉声のなかに、さまざまな人生が息づいています。(IH)

- 作者: 橋口譲二
- 出版社/メーカー: 文藝春秋
- 発売日: 1988/04
- メディア: 大型本
- クリック: 1回
- この商品を含むブログ (2件) を見る

- 作者: 橋口譲二
- 出版社/メーカー: 角川書店
- 発売日: 1998
- メディア: 単行本
- 購入: 1人 クリック: 4回
- この商品を含むブログ (6件) を見る
『170のkeywordによる ものづくり経営講義』
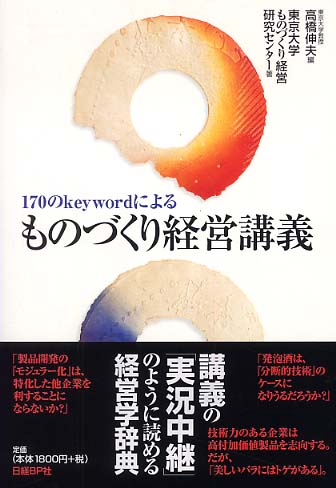
高橋伸夫 編、東京大学ものづくり経営研究センター 著、2005/09 日経BP社 A5判/230ページ 定価 1,890円(税込み)ISBN:4822244709
「製品開発の『モジュラー化』は、結局、川上・川下に特化した他企業を利することにならないか?」「発泡酒は、『分断的技術』の例になりうるだろうか?」「性別、年齢、職業などの『デモグラフィック属性』は、日用消費財のブランド選択を説明できるだろうか?」――170のキーワード講義と、それに続く魅力的な設問・解答(追加講義)によって、ものづくり経営の最先端が無理なく頭に入るレクチャー形式の経営用語辞典。東大ものづくり経営研究センター教授陣らの実際の講義に基づく、初学者向けの「ものづくり経営」のエッセンスの集大成。
第1講 競争戦略 第2講 オペレーション管理 第3講 品質経営 第4講 アウトソーシング 第5講 アーキテクチャ 第6講 大量生産方式 第7講 カスタマー・エクイティ 第8講 マーケティング戦略 第9講 組織論 第10講 日本の経営の原点 第11講 日本の経営者列伝
プロジェクトマネジメントとエスノグラフィー
http://people.weblogs.jp/books/2005/06/post_794e.html
ヘンリー・ミンツバーグ(奥村哲史、須貝栄)「マネジャーの仕事」、白桃書房(1993)
戦略論のグル ミンツバーグの書いたマネージャーのエスノグラフィー。
組織の中でもっとも定義しにくい仕事は、いうまでもなくマネージャーの仕事である。そのマネージャーの仕事について、エスノグラフィーを行い第3章 マネジャーの仕事にある明確な特徴
第4章 マネジャーの仕事上の役割
第5章 マネジャーの仕事の多様性
第6章 科学とマネジャーの職務という視点で1冊の本にまとめている。

- 作者: ヘンリーミンツバーグ,Henry Mintzberg,奥村哲史,須貝栄
- 出版社/メーカー: 白桃書房
- 発売日: 1993/08/26
- メディア: 単行本
- 購入: 3人 クリック: 36回
- この商品を含むブログ (22件) を見る

- 作者: Henry Mintzberg
- 出版社/メーカー: Harpercollins College Div
- 発売日: 1973/01/01
- メディア: ペーパーバック
- この商品を含むブログ (3件) を見る

- 作者: Henry Mintzberg
- 出版社/メーカー: Prentice Hall
- 発売日: 1980/01/01
- メディア: ハードカバー
- この商品を含むブログ (1件) を見る
from プロジェクトを成功させる仕事術 pm_work_style: エスノグラフィーしよう! http://people.weblogs.jp/pm/2005/08/post_014b.html
僕はコンサルティングの中に、エスノグラフィーに取り入れている。エスノグラフィーとは、現場に行って人々の行動を観察し、その行動をドキュメント(モノグラフという)に書き留めておき、ドキュメントを分析してさまざまな知見を得ようという一種のフィールドワークの手法である。
弊社の場合は、ただ観察するだけではなく、実際にプロジェクトに参加して(例えば、プロジェクトマネージャーやプロジェクトマネジメントスタッフを引き受けて)、その中で観察をしていくという「参加観察」の手法をとることもある。
もともと民俗誌をつくるために使われていた手法だが、マネジメントの中でも、組織の問題を扱う場合などを中心に疲れるようになってきた。民俗誌の場合、やはり、一緒に生活してみないと分からないことも多いらしい。マネジメントでも同じような意味で、貴重な情報が得られることが多い。
僕がエスノグラフィーを使うに至ったのは、いろいろな人や本からのアドバイスがあったからだが、最も、影響の大きかったのは、ヘンリー・ミンツバーグの
という本を読んだこと。マネージャーに持っている実際のイメージと、実態はこんなに違うものかということに驚かされた。まさに臨床の知である。
この本を読んで以来、人の話を聞いて診断をするということをしなくなった。生産管理などのコンサルティングでは現場を見るのが常識だが、人が絡んだ部分では、なかなか、難しい。そのため、観察するよりはインタビューが中心になっていたのだが、考えを改め、エスノグラフィーを取り入れるようにした。
from pmstyleゼミナールプロジェクトマネジメント: ゆとりをもって仕事をしよう(2) http://people.weblogs.jp/pmstyle/2005/08/post_5c3a.html
ゆとりをもって仕事をしよう(2)
ある年に、CADを開発している企業(部門)で、5ヶ月をかけて延べ18日間のエスノグラフィーを 行ったことがある。テーマはプロジェクトマネージャーの仕事とコンピテンシー。書いたものは門外不出なのだが、非常に多くのことが分かった。まさに、百聞 は一見にしかず。
見た目に、Aのメンバーは余裕を持って仕事をしている。朝礼で時間がかかる場合でもしっかりとした議論をしている。他のメンバーの予定に変更があってもほとんど手待ちをすることなく、自分のスケジュールの修正をしている。
ところがBの方は、バタバタ。何か変更があろうものなら、みんなが走り回る状態になる。普段もまったく余裕がない。追い詰められたような雰囲気で仕事をしている。
この2つの差はどこにあるのだろうか?はっきりしているのは、Aプロジェクトはそれぞれのメンバーに全体の動きが見えている。その上で、自分の判断で毎日どのように行動すべきかを決定している。自立するとはそういうことだ。
Bはメンバーに全体の動きが見えていない。したがって、すべての変化は突然やってくるので、その対処に追われる。
結果として現れるのは大きな違いであるが、実はこの違いはそんなに大きな違いではない。プロジェクトマネジメントの概念に「プロアクティブ」という概念がある。日本語でいえば、先手必勝。最初の手が自分から打てるかどうかの違いである。
プロジェクトAのプロジェクトマネージャーはメンバーの先手必勝をうまく演出している。プロジェクトBのプロジェクトマネージャーはそれがあまりう まくできていない。その違いだ。先手必勝によりゆとりが生まれる。ゆとりはゆとりを生み出す。その原資となるゆとりを如何に生み出すかがプロジェクトマネージャーのスキルである。
『確率的発想法 数学を日常に活かす』NHKブックス
from Hiroaki Suzuki's Blog: 確率的発想法
阿部さんのページに確率的発想法という本がとても優れた本であるという紹介がだいぶ前にあったので読んでみた。
確かに基本のところ(知らないことが多かったのですが)をとてもわかりやすく解説しているだけでなく、かつ先端的な研究の話まで拡張してあり、とても好感が持てた。Maxminとか、自己責任、公共性、正義、確率の時間性など、いわゆる確率の本にはあまり書いていないような広がりがいろいろと見えてきたことがとてもよかった。またそれらの問題に対する著者のスタンスにも強く共感。たとえば、自己責任を問える条件として、
・ルールの公平性(理解可能性)
・効用、選好についての完全知
・参加回避の自由
が挙げられており、これらが満たされることは現実世界では究めてまれという主張など。あえて言えば、「決め方の論理」が取り上げられていないのはやや疑問。

- 作者: 小島寛之
- 出版社/メーカー: NHK出版
- 発売日: 2004/02/29
- メディア: 単行本(ソフトカバー)
- 購入: 60人 クリック: 218回
- この商品を含むブログ (88件) を見る

